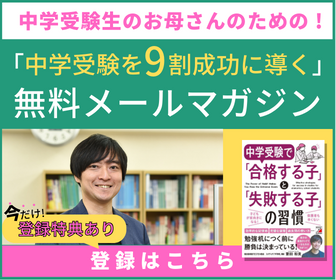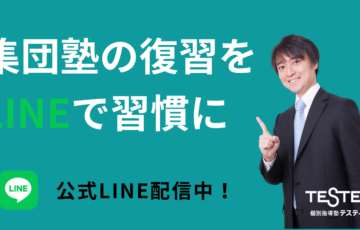中学受験の化学に苦手意識を持っていませんか?化学分野は、覚えるべき知識も多く、また、その知識をもとにした計算問題が入試でよく出題されます。「化学の計算問題」というと苦手意識を持ってしまう受験生はとても多いです。算数の計算問題は頑張ってやるけれど、化学の計算問題、と言われると身構えてしまう・・・なぜ苦手意識を持ってしまうのでしょうか。
今回は、その原因と、化学の計算問題がこわくなくなる勉強法をご紹介します。
Contents
なぜ苦手になるのか?
そもそも化学分野で覚えるべき知識を覚えていない
そもそも、化学分野で覚えなければならない知識が少ないと、化学の計算問題は解けません。化学の計算問題はあくまで、化学のしっかりした基礎知識をどのように使えるようになっているのか、それを見るために出題されています。物質の性質の知識はもちろん、入試問題でよく取り上げられる実験が何を行うものなのか、たとえば、燃焼の実験なのか、気体の発生の実験なのか、物質の溶け方を調べているものなのか、などの意味がわかっていなければ、計算問題を解こうにも、計算の戦略を立てることができません。
算数の基礎知識不足、計算力不足
さらに、算数の知識がないと解けません。たとえば、割合は算数の基礎(考え方は基礎ですが、いろいろな問題が作れるので、難しいという意識を持っている受験生は多いでしょう)ですが、これを応用した考えは化学だけでなく、理科の単元では数多く出てきます。算数の基礎ができていないと理科の計算問題は解けません。比やグラフなどの算数の知識は、理科でもよく出てきますね。
基礎的な計算だけでなく、つるかめ算など、中学受験ではおなじみの計算も化学では活用することがあります。算数と理科の化学・物理は密接な関係があるのです。
どのように勉強するか
まず基本知識、基本原理を理解する
化学の計算に苦手意識がある人は、まず化学の暗記すべき知識を確実に理解し、覚えるよう努力しましょう。ものの燃え方の仕組みや物質の性質、気体の発生のさせ方、集め方などはしっかり仕組みを理解して覚えておきましょう。また、水溶液と濃度の原理、酸とアルカリなどの性質について、さらには物質ごとに単位あたりの重さは決まっていて変わることがないことなど、基本原理を理解しておくことが、まず前提です。
発想の転換も必要
そして実際に問題を解くときには、まず問題で問われていることを図に表すくせをつけましょう。これは算数の応用問題を解くときも同じですね。また、化学の計算問題は「理科の計算」と意識しすぎないのがコツです。つまり、「算数の問題と考える」という発想の転換をしてみてください。
たとえば、「銅と酸素の化合の重さの比は4:1ですが、ある実験をしたら反応していない銅が〇グラムありました・・・」という問題や、「塩酸に鉄を溶かすと〇グラムの水素が発生します・・・」という問題は、よく見たら算数の問題であることが少なくありません。算数になると、銅や酸素や水素の代わりに、塩や砂糖やしょうゆを使った問題に置き換えられたりしていますが、本質は同じです。
「銅と酸化銅の重さの関係を表したグラフは・・・」という化学の問題は、「1分間に〇リットルの水が出る水道で、ある容器に水を入れると〇センチずつ、水かさが増していきます。その様子を表したグラフは・・・」という算数の問題と考え方は同じです。比や、直線の式のグラフになりますね。
化学の計算問題が得意な受験生は、このような発想の転換ができているようです。算数の計算が得意であれば、化学の計算はむしろ易しく見えてくるようですね。算数の応用問題にくらべると、条件が詳しく書かれていることが多いですから、化学の計算問題はヒントがたくさんある算数の問題、と考えてみると、「やったことがある」問題に見えてきますよ。
化学の計算問題はこわくない
化学の計算は、たしかに慣れは必要です。ですが、算数の基本的な計算ができればこわいものではありません。特に、比の計算は間違いなくできるようにしておきましょう。また、理科は分数ではなく、小数で解答するので、小数の計算が苦手だと苦労してしまいます。四捨五入の概念や概数の計算についても、算数の計算の基本ですね。迷わず処理できるように、きちんと理解することが必要です。
ただし、難関校の入試では特殊な計算を必要とすることがありますので、さらに高度な計算力が求められます。つるかめ算や面積の求め方についてもしっかり理解を深めておきましょう。それぞれの算数の単元の基本理解をしっかりしておき、化学の計算の場面でも「使える」ように練習しておくことをおススメします。
<関連記事>
一橋大学卒。
中学受験では、女子御三家の一角フェリス女学院に合格した実績を持ち、早稲田アカデミーにて長く教育業界に携わる。
得意科目の国語・社会はもちろん、自身の経験を活かした受験生を持つ保護者の心構えについても人気記事を連発。
現在は、高度な分析を必要とする学校別の対策記事を鋭意執筆中。