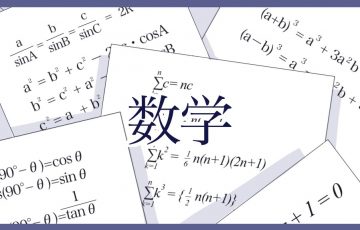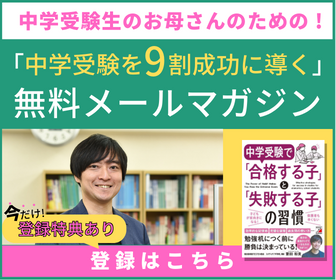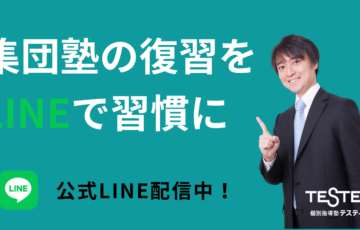Contents
「文系」って何をしているの?
高校での教科のイメージから……
一度高校で文系と理系に分かれてしまうと、大学では全く違ったことを学ぶようになり、さらに、理系が研究室に入り浸りの一方で、文系は家で勉強している(本当にそうかな……?)といったように、ライフスタイルまで全く変わってしまうのです。理系からしたら、文系の生活は謎に包まれており、また、何を学んでいるのかもなかなかわからないということがあります。
このことは、実は高校での文系科目・理系科目の性格の違い(に見えるもの)とも関係しているでしょう。理系科目、例えば物理が、決められた条件で実験をするときにどうなるか計算によって考える一方で、物理学者は計算によって考えた後に実際に実験を行い新しいものを生み出すというイメージがある。ここでは、高校の勉強から大学での勉強がイメージできる。
一方、例えば国語に関して言えば、そもそも「運ゲー」「才能」の問題かもしれない(そんなことはないのですが)謎の科目であり、文学について研究するということがどういうことかは掴みづらい。確実に、文学研究には、国語の試験のような「設問」はないのですから、高校までの勉強とは何かが違うのだとは思うけれど、じゃあどういうものか、なかなかわからない。
厳密には「文系」=何やってるかわからない、ではない
文系学生が必ずしもこの「何かわからない」学問をやっているわけではありません。例えば、法学部の学生は、多くの場合、法律に関する知識を広く身につけ試験に合格することを目指しており、これはわかりやすい。あるいは、心理学だったら(これは日本では文系なのですが)、心について今ある理論から言えそうなことを実験して、データを分析してその理論を更新していくという点で「理系」的です。
謎に包まれているのは、文系の中でも「人文学」と呼ばれる領域の勉強をしている人たちです。例えば、哲学、宗教学、歴史学、文学といった学問がここに含まれる(この呼び方で心理学を含んだり含まなかったりしますが、今は含まないでおきましょう)。彼らは何をしているのでしょうか。
学問としての「文学」——作品の豊かさを取り出す
少なくとも題材はわかる「文学」について見てみましょう。『走れメロス』を例えば題材にしたとして「文学研究」とは何をすることになるのでしょうか。まず言えるのは、あらすじを語るということではない。それは、文学を研究するその人物でなくてもできることです。文学研究にあって、研究者ができることは、作品の内部にあり誰でも手に取れるような何かを語ることではない。そうではなく、作品の奥にあって、まだ表面に現れていないもの、その奥行き、広がり、豊かさを取り出すことです。
「表象分析」という方法
例えば、太宰はなぜギリシア人を走らせたのでしょう? こうした問いの答えは作品の中には存在しません。しかし、問いそれ自体は、作品の中に眠っている(国語の授業の初っ端「なんでギリシア人なのですか?」と先生に聞く生徒は周りから「空気が読めないやつ」だと思われたとしても文学研究にはぴったりの人物です)。この問いについて、太宰の時代の「ギリシア人」に対する見られ方を太宰自身の文章や当時の歴史資料を振り返りながら整理していくということは間違いなく研究になるでしょう(「表象分析」と言います)。そしてそれは間違いなく、作品の経験を豊かにします。それは、こうした研究が、太宰がメロスを走らせたという事態の奥に走っている事柄を浮き彫りにし、分析を読んだのちは、メロスを一人のギリシア人として読む全く新たな観点、ランナーを追いかける別の視点のカメラ——正月の箱根駅伝を思い出しましょう——が生まれるからです。

太宰治(1909-1948)
表象分析が大きく成果を上げている研究領域として、例えば、ジェンダー研究、すなわち、男性/女性の社会的なありようについての研究があります。なぜ「お姫様」が「王子様」に救われるのか? なぜ「キス」で目覚めるのか? といったことは、そこで描かれている「女性」とは何か? という問題と結び合わされたとき十分研究になります(あるいは、いつの時代から「戦う女性」が作品に現れたのか、『リボンの騎士』ではまだ「男装した女性」だったが、今では女子高生が変身する……彼女たちのあり方はどう変わっていったのか、それは社会における女性のどのような位置付け変化と関係するのか……。こうした分野の研究としては若桑みどり『お姫様とジェンダー』や河野真太郎『戦う姫、働く少女』といったものがあります)。

女性はいつから戦えるようになったのでしょう?
「テキスト論」という方法
文学研究に関しては、一方で全く違う角度から問いを立てられるかもしれません。彼らは、「なぜ太宰はこうしたのか」「この作品はいかに社会の〇〇の描かれ方を反映しているのか」といった問題設定に対する「都合の良さ」を指摘します。別に太宰は何も考えずただギリシア人を走らせたかったのではないか? ただ女性を描いたらそうなったのではないか? などなど。そうだとすれば、研究はどの方向に向かっていくのでしょうか。例えば、我々の読書経験それ自体に着眼して文学研究を行うアプローチが考えられます。
ピエール・バイヤール『読んでいない本について堂々と語る方法』は、そうしたアプローチをとるまさしく名著です。本を読んでいるとき、もちろん私は眠かったり、関心が他所に行ってたりする。読みきって100%本の内容が頭に入っているということはありえない。バイヤールはそのことを確認します。その意味で、我々は本を「読んでいない」ということができる。それでも、我々は感想を生み出すことができます。夏休み最終日に読書感想文を書くとき、確実に流し読みしているけれど、なんとなくストーリーと思ったものに、それに関係しそうな自分の経験を重ねて「本について語っているかもしれない何か」を書く。バイヤールはそれを全肯定するわけです(なんてったって『語る方法』の最後の節のタイトルは「自分自身について語る」なのですから!)。

まさにこの時にこそ本を読んでいる!
本を読むときに起きていることは、さまざまな事柄の関係づけと見ることができるわけです。先の太宰研究だったら、当時の「ギリシア人」と、作品中のギリシア人を関係づけた一つの読みであるというふうに言える。そして、そうした関係づけ自体が、豊かさを生み出しているわけです。和歌の「本歌取り」(過去の歌のフレーズをリフレインして、今描いている景色をそのレンズを使ってみることです)は、こうした関係づけです。今見える景色に見知っている歌が一つの奥行きを生み出している。その奥行きをそのまま表現するために、歌を引用するわけです。あるいは、小学生の頃友達と一緒に歩いた帰り道が、そのころの思い出と重なってえも言われぬ感動を生み出しているときに起きていることもこうした関係づけです。思い出が一つの「本」——こういうときには「テクスト」と呼ぶことが多いですが——のようにみられ、そのテクストの重ね合わせが、今の単純ではない見えを生み出しているわけです。

帰り道は一つのテクストである
文学研究は、重ね合わせから一つの見えが形成されるということ、世界の複雑性とも言えようそうした事態を切り捨てずに直視しようとすることを作品研究と理論の水準で行なっていると言えそうです。私の考えでは、哲学もより抽象的なところで同じ問題を検討をしていると言えると思います。哲学は、ある概念から世界が現れるということを、我々の見えのうちには、そもそも、複雑な過程、重ね合わせの過程があるということを考えている。
学問としての哲学——世界の豊かさを考える
偶然性の哲学者 九鬼周造
たとえば、九鬼周造(1888 – 1941)は「偶然」という観点から、偶然と必然との重なり合いとして世界にアプローチしました。彼にとって現実は「出会い」の経験から構成されます。私が誰かに出会うという日常的な出会いだけでなく、私があるものを見ることは、私とそのものとの出会いとして、私がある立場にいることは、私とその立場との出会い(「求人サイトで仕事を見つけた」とか…….)というふうに言えるでしょう。もちろんその立場に出会うためにも、それ以前の出会いが(例えば「ある趣味と出会ってしまったが故に、貧困に出会い、仕事と出会わざるを得なくなった」というように)あるといえます。
そうした出会いの中には「偶然の出会い」と呼びたくなるものがあると思います。運命の人との出会いを「運命」と呼んでおきながらも「偶然」だと言いたくなるのは人のさがです。しかし九鬼によればそこで「偶然」を考えるのはヤワである。というのは、私がその人と出会うことは、私とその人のそれぞれの必然の論理に従っているかもしれないからです。私はこれこれこういう理由でこの大学に入った。一方その人はこれこれこういう理由で同じ大学に来た。お互い各々の理由で同じ講義を取った、だから出会った。そもそも私が大学に入った理由は私の生い立ちに由来するが、そこでもそういう生い立ちを送ることは社会的条件から「必然」であった……。ヤワな偶然では必然に対して勝つことができないのです。そしてもし全てが(わかりはしないとはいえ)必然なのだとしたら、偶然の出会いに驚く私たちはただのバカだということになってしまう。

「カレ」と偶然の出会いをする女の子にも走らざるをえなかった「必然」があります
九鬼はその必然の上に真の意味での偶然(「原始偶然」)を打ち立てます。AとBとの一見偶然的な出会いには、それを規定するA’, B’があった。そうしたA’, B’が生じるところにも(先の「社会的条件」)さらに偶然があるかもしれない。しかし、それもさらに実の所必然性に支配されているかもしれない(条件を規定したある事件は、実はそれを起こした犯人の精神状態がこうだったから……)。このように偶然に対して常に必然が先行しているとして、しかし、全く最初の偶然を規定するような(そしてその後の偶然を全て規定するような)最初の必然はいかにして起きたのでしょう? 私とあなたとの出会いはこうして「宇宙の始まり」ともいえよう地点にまで遡ります。そこで起きること、全ての出来事を必然に決めてしまうような最初のビッグ・バンそれ自体は、しかし、偶然でしかあり得ません。他の様々な「宇宙」が生まれてもよかったのに、その「宇宙」であることは、それがもう遡れない最初の一点である以上、「ぽっと」出た偶然でしかあり得ないのです。我々を支配しているように見える必然の上にこの「原始偶然」を打ち立てること、そのことによって、世界は再度偶然性を取り戻し、私はあなたとの出会いの中に、宇宙の始まりの偶然、その驚きを経験することができるのです。

一つの出会いの「偶然性」は宇宙が今のようにあることへの偶然性に通じている……
世界を構成する様々な概念を考えてみること
哲学者はおのおの、このようにある断片から世界がいかに構成されるかについて思考しています。イマヌエル・カント(1724 – 1804)は私と自然とが交流して今ある世界が出来上がるために私が世界をどのようなものとして見るか、そのフレームを考えました。エマニュエル・レヴィナス(1906 – 1995)は私が自然に寄りかかった状態から一人の人として、世界に浸りきるのではなく意味付けなければならなくなるような〈他者〉との出会いについて考えましたし、精神分析は母子関係とそこに入り込んでくる父との関係から、心の病を、欲望を、世界の意味づけを考えました。
哲学をするということはそのような見えを構成する契機を編み出して、そこからいかに世界が成るかを考えることであり、誰々の哲学を研究するということは、その成り方について再検討することにほかなりません。それは、九鬼が必然性のネットワークから驚きを取り戻したように、世界をより豊かに経験する道を探るということでもあります。
人文学は「豊かさ」に向かう——世界の価値を可能にする人文学
人文学は何をしているのか
人文学、そのうち文学と哲学の二つを見てきましたが、それらは各々の仕方で、現実をより豊かにするために新たな視点を作ろうとする営みだということができると思います。
歴史学や宗教学については僕も詳しくはないのですが、やはり同様でしょう。そこでは、過去の史料の集積(歴史学ならば当時の国の記録や日記などが、宗教学ならばそこに信者が自分の信仰について書いた文章が加わるでしょう)からいくつかを選んで、一つの筋を作るわけです。すると「ネイティブ・アメリカンの側から見たアメリカ独立」や「女性の側から見た太平洋戦争」「善い行いによって人は救われるのか(「行為義認」)、信仰によって救われるのか(「信仰義認」)、その考え方の歴史的変遷」みたいなものが現れてきて、現時点の世界だけを見ているのとは違った豊かな経験が生まれてくる。
人文学は役に立つのか
文系学問についてはよくそれが「役に立つのか」ということが語られます。それは、単に雑談のトピックというだけでなく(それだけだったらどんなによかったことか!)、彼らの研究を食わせてやるべきかという生き死にの水準で語られていることなのです。たしかに(一部の)理系学問がもたらす物質的な豊かさを文系はもたらさないかもしれない。しかし、もしそうした豊かさを享受する人間の側にそれを経験するための土壌が、眼差しの強さがなければ、結局は学問も、人間の活動の全ても価値を失ってしまうのではないでしょうか。私は自分が専門としている人文学の意義をそのような地点に見ています。
(ライター:菊池)
おすすめ記事
参考
- 河野真太郎『戦う姫、働く少女』
- 九鬼周造「偶然の諸相」(『人間と実存』所収)
- ピエール・バイヤール『読んでいない本について堂々と語る方法』
- 若桑みどり『お姫様とジェンダー』
- いらすとや(2021年7月8日アクセス)
東京大学文科III類出身、現在は哲学系の学科にいます。
数学の記事のほか、専攻に近づけて「勉強論」みたいなこともこれから書いていきたいと思っています。
読書のほか、昔のアメリカ・フランス映画を観たり、料理したりするのが好きです。いつの間にかつまらなくなった勉強の中に、新しいことを知ったり、できるようになった時のうれしい気持ちが戻ってくるような記事を書きたいです!