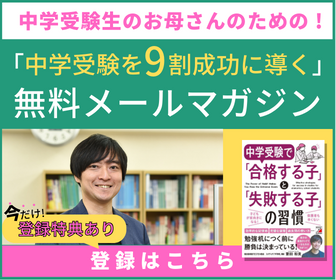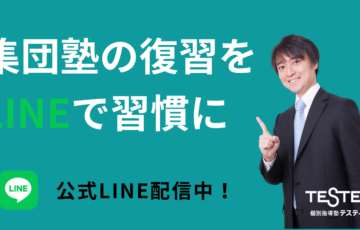『蜻蛉日記』は、上・中・下の三巻からなる夫婦生活の記録を綴った初の女流日記文学です。作者は平安時代中期の歌人、伊勢守藤原倫寧[i]の娘である藤原道綱母です。作者藤原道綱母が天暦8年(954年)に藤原兼家[ii]と結婚したところから始まり、天延2年(974年)で終わっています。その後長徳元年(995年)頃に藤原道綱母が没したとされています。『蜻蛉日記』は日記が終わっている天延2年(974年)から没するまでの期間で編纂し、成立したのではないかと考えられています。
『蜻蛉日記』の内容について触れる前に、作者藤原道綱母及、当時の婚姻関係について説明したいと思います。
先に述べた通り、藤原道綱母は天暦8年(954年)に藤原兼家に嫁ぎました。しかし既に藤原兼家は正妻時姫(藤原道長の母)がいました。平安時代は一夫多妻制ですが、複数の妻の中にもランク付けがあり、その一番上の位にいるのが正妻です。父方の血筋の良い女性などを正妻として迎え入れ、その他にも妻がいるというわけです。妻は三日の儀を執り行い、結婚した者のみとし、儀式を執り行わなかった場合は愛人となります。立場としては正妻が一番上ですが、結婚した後も夫が足繁く通うには、後継ぎとなる男児を産むこと、和歌などで夫の気を引くなど努力が必要になります。当時、貴族の女性は親と夫の援助なしには生活出来ず、夫に捨てられボロボロになった家で夫の訪問を待ち続けるしかない女性や、やむなく都を離れた女性も多くいました。藤原道綱母は結婚した次の年には藤原道綱を産み、正妻時姫より寵愛されていたと考えられることが多いですが、『蜻蛉日記』ではそのような幸せな様子は描かれず、愛人を作って自分のもとに通いに来ない兼家に対する嘆きに多くの筆を割いています。
このことがよく分かる『蜻蛉日記』上巻の序文を紹介します。
はかない身の上(一)
かくありし時過ぎて、世の中に、いとものはかなく、とにもかくにもつかで、世に経る人ありけり。容貌とても、人にも似ず、心魂も、あるにもあらで、かうものの要にもあらであるも、ことわりと、思ひつつ、ただ臥し起き明かし暮らすままに、世の中の多かるそらごとだにあり、人にもあらぬ身の上まで日記してめづらしきさまにもありなむ、天下の人の、品高きやと、問はぬ例にもせよかし、と、おぼゆるも、過ぎにし年月ごろの事もおぼつかなかりければ、さてもありぬべきことなむ、多かりける。
〈訳〉
こうして女盛りの時もむなしく過ぎ去ってしまって……。ある所に、ひどく頼りなく、夫のある身とも独り身ともいえないような状態で暮らしている女がいたのである。それほどの美人というわけでもなく、しっかりした考えがあるともいえず、こうして役に立たず生きているのも当然だと思いながら、ただ、寝ては起きるようなむなしい日々を暮らすなか、世の中にたくさんある古い物語をのぞいてみると、どれもこれもきれいごと、うそばっかり。そんなものでさえおもしろがられるのだから、人並みでない私の身の上をありのまま日記にしたら、もっと珍しいものになるだろう。最上の身分の男との結婚生活の真相は、と聞かれた時の実例にでもしたらよい……。とは思うものの、過ぎ去った日々の記憶は薄れ、まあまあ許せる程度のことが多くなってしまった。(角川ソフィア文庫『蜻蛉日記』参照)

本来、「日記」は男性の書き手によって漢文で書かれるものが多く、公的な意味合いを持つものでした。しかし、「男が書いている日記というものを女の私も書いてみよう」という書き出しで始まる紀貫之[iii]の『土佐日記』から「日記」の意味合いが変わってきます。紀貫之は私的な内容を日記として書き留めましたが、その中では日記文学として題材が選ばれ、脚色されています。その後に成立した『蜻蛉日記』もまた、『土佐日記』を継承していると考えられています。先に紹介した『蜻蛉日記』の序文に「かくありし時過ぎて、世の中に、いとものはかなく、とにもかくにもつかで、世に経る人ありけり」とあるように『蜻蛉日記』に描かれるテーマは夫である藤原兼家との“はかない夫婦生活”です。

では、それぞれの巻の内容について詳しく見ていきたいと思います。
- 上巻
兼家の求婚から始まり、結婚。次の年には道綱が産まれる。順調に見えた結婚生活のはずでしたが、父が陸奥(現在の青森県全域と岩手県の北西部にあたり)に赴任し、母が亡くなり、町の小路の女という兼家の浮気相手が出現し、妊娠といった様々な不幸に見舞われます。また、作者は道綱しか子供を授かりませんが、時姫は三男二女に恵まれます。(三男が藤原道長) - 中巻
作者方と時姫方の従者が乱闘する事件が起きます。その結果、作者は少し離れた所に転居します。その後、兼家は東三条邸に新居を建設しますが、新居に迎え入れられたのは時姫母子だけで、時姫と作者の立場の差が大きく開いていきました。この巻の特徴として、独詠歌が多いことがあげられます。通常、歌の多くは男女間で贈り合う贈答歌です。一方で、独詠歌は「独りで詠んだ歌」のことです。そのため、独詠歌が多いということは「相手にされず独りでいることが多い」ということを意味しています。 - 下巻
今までの夫婦生活中心に描かれていましたが、下巻になると描かれなくなっていきます。広幡中川に作者が転居した後兼家の来訪もなくなります。下巻で中心的に描かれるのは、作者が迎えた養女と養女に求婚した右馬頭遠度の物語です。

上巻、中巻に比べ、下巻は巻全体の趣が大きく変わっています。実際に作者が見聞きしたものではない記述が見受けられ、その内容は日記文学を超えて物語として終着を迎えようとしている姿勢が見受けられます。このことに関して、坂口由美子は「俯瞰するような視点や物理的な時間に縛られない自由な進行など、作者の筆は日記の枠を超えつつある」[iv]と指摘しています。
その様子が分かる最後の幕を紹介します。
暮れ果てる日(二〇九)
今年、いたう荒るるとなくて、はだら雪、ふたたびばかりぞ降りつる。助のついたちの物ども、また、白馬にものすべきなど、ものしるほどに、暮れ果つる日にはなりにけり。明日の物、折り巻かせつつ、心に任せなどして、思へば、かう長らへ、今日になりにけるも、あさましう、御魂など見るにも、例の尽きせぬことにおぼほれてぞ、果てにける。京の果てなれば、夜いたう更けてぞ、たたき来なる。(とぞ本に。)
〈訳〉
今年は、天候がひどく荒れることはなくて、小雪が二度ばかりちらついただけである。助(道綱)の元日の装束など、また、白馬の節会に着て行くものなど用意するうちに、大晦日になってしまった。明日の御祝儀の反物などを折らせたり巻かせたり、侍女たちに任せなどして、考えてみると、このように生きながらえて今日まですごしてきたのもあきれるばかりで、御霊祭などを見るにつけ、いつものように尽きない物思いにふけっているうち、今年も終わってしまった。ここは京の外れなので、夜がすっかり暮れてから。追儺の門をたたく音が近づいて来る。(角川ソフィア文庫『蜻蛉日記』参照)
最後の幕になると、兼家の訪れが途絶えて久しくなっており、作者はもう兼家との関係に思い悩み、荒れることもなくなります。世間との繋がりは息子の道綱のみで、世間との繋がる方もかなり消極的になっています。そして、「そのまま終わりを迎えるのでしょう」という独白で『蜻蛉日記』は終わりを迎えます。『蜻蛉日記』はその後の日記文学をはじめ、多くの作品に影響を与えてます。
最後に『蜻蛉物語』について簡単な問題を出したいと思います。
(わからなかった問題はしっかりと復習しておこう!)
- 『蜻蛉物語』の作者は誰ですか。
- 作者は誰と結婚しましたか。
- 問2の人物は作者の他に誰と結婚していますか。
- 『蜻蛉日記』以前に出来た日記文学は何ですか。
- 作者の子供は誰ですか。
→次回は宇津保物語について解説します!
(註)
- [i] ?-977 平安時代中期の官吏。
左馬頭(かみ)藤原惟岳の子。母は源経基の娘。陸奥(むつ)などの国守を歴任し,没時は伊勢守(いせのかみ),正四位下。娘に藤原道綱の母(「蜻蛉(かげろう)日記」作者),孫に菅原孝標(たかすえ)の娘(「更級(さらしな)日記」作者)がいる。貞元(じょうげん)2年死去。『日本人名大辞典』 - [ii] (929~990) 平安中期の廷臣。師輔の子。兄兼通と対立。兄の死後、花山天皇を退位させ、外孫一条天皇をたて摂政・関白となった。『三省堂 大辞林 第三版』
- [iii] (866?~945?) 平安前期の歌人・歌学者。三十六歌仙の一人。御書所預・土佐守・木工権頭。官位・官職に関しては不遇であったが、歌は当代の第一人者で、歌風は理知的。古今和歌集の撰者の一人。その「仮名序」は彼の歌論として著名。著「土左日記」「新撰和歌集」「大堰川おおいがわ行幸和歌序」、家集「貫之集」『三省堂 大辞林 第三版』
- [iv] 角川ソフィア文庫『蜻蛉日記』参照
おすすめ記事
参考文献