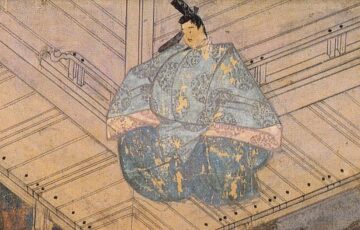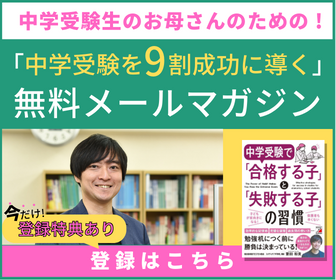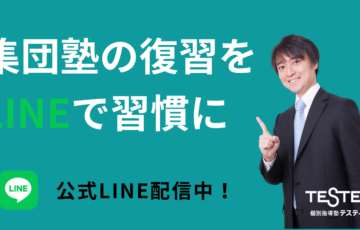『和泉式部日記』は平安中期の日記文学です。作者は和泉式部だと考えられていますが、第三者によって書かれたという説もあります。その理由は、他の日記文学、例えば『蜻蛉日記』や『紫式部日記』は主人公が作者であり、主人公が経験したことが書かれている一方、『和泉式部日記』で描かれるのは主人公が経験していないことであり、人物の観点に統一がないためです。他にも、主人公である「和泉式部」が「女」という三人称で記されていることも理由として挙げられています。内容は、贈答歌を中心に冷泉天皇の第四皇子である帥宮親王と和泉式部の恋愛を中心に描かれています。

『和泉式部日記』について解説する前に、主人公である和泉式部という人物に触れたいと思います。
和泉式部は平安時代の歌人であり、父は越前[i]守大江雅致、母は越中守平保衡の娘です。越前守の“守”というのは今でいう地方の役人にあたります。母は冷泉天皇[ii]の皇后昌子[iii]に仕えており、介内侍[iv]と呼ばれた女房[v]でした。母に付き添って和泉式部も少女の頃から宮仕えをしていたと考えられています。その後、和泉式部は橘道貞[vi]と結婚し、橘道貞が和泉[vii]守になったことから“和泉式部”と呼ばれることになりました。“式部”とは宮中に使える女房(女官)の役職を指す言葉です。橘道貞が任地に赴任し、和泉式部は宮中に仕え、冷泉天皇の第3皇子である為尊親王[viii]と恋仲になりますが、程なくして為尊親王は疫病のため亡くなります。悲しみに沈んでいる和泉式部はその弟皇子(同母)である敦道親王[ix]と恋仲になります。その後、藤原道長[x]の娘である中宮彰子[xi]に仕えました。そのように2人の親王に愛された和泉式部は宮中でも有名な“恋多き女”でした。その様子がわかるエピソードとして、藤原道長に和泉式部が戯れに「浮かれ女」とよんだ話があります。
『和泉式部日記』には先に説明した通り、恋多き女・和泉式部の奔放な恋の様子が描かれています。恋に奔走する一方で、和泉式部は夫である橘道貞に去られ、親からも勘当されています。日記中には、そのような切ない我が身、忍んでいた恋も世間の噂となり、宮の心が離れてしまったことなどがありありと描かれています。
このことがわかる場面として、宮の訪れがなくなり寂しい気持ちを慰めるために石山寺[xii]を訪れた和泉式部の様子を描いた段を紹介したいと思います。
かかるほどに八月にもなりぬれば、つれづれもなぐさめむとて、石山に詣でて七日ばかりもあらむとて、詣でぬ。宮、久しうもなりぬるかなとおぼして、御文つかはすに、童、「一日まかりてさぶらひしかば、石山になむこのごろおはしまなる」と申さすれば、「さは、今日暮れぬ。つとめてまかれ」とて御文書かせたまひて、たまはせて、石山に行きたれば、仏の御前にはあらで、ふるさとのみ恋しくて、かかる歩も引きかへたる身の有様と思ふに、いともの悲しうて、まめやかに仏を念じたてまつるほどに、高欄しものかたに人のけはひすれば、あやしくて見下したれば、この童なり。
あはれに思ひがけぬところに来たれば、「なにぞ」と問はすれば、御文さし出でたるも、つねよりもふと引きあけて見れば、「いと心深う入りたまひにけるをなむ、などかくなむとものたまはざりける。ほだしまでこそおぼさざらめ、おくらかしたまふ、心憂く」とて、関越えて今日ぞ問ふとや人は知る思ひたえせぬ心づかひをいつか出でさせたまふ」とあり。
(『日本古典文学全集 和泉式部日記』より参照)

この場面はつれづれの気持ちを慰めようと石山詣に出かけたことから始まります。世相から離れ、物思いにふける和泉式部の元に人伝に石山にいつことを知った親王から文が届きます。思いがけない手紙に普段よりも急いで読もうとする和泉式部の姿に石山まで来て仏の前で祈っても捨てられない恋心がうかがえます。
このような和泉式部の奔放な恋の様子だけでなく、日記文学でありながらその和歌の数の多さも『和泉式部日記』の特徴といえます。その多くが贈答歌であるため、冒頭で述べたように、贈答歌を元にして第三者が書いたのではなかと考えられています。
では、最後に『和泉式部日記』について簡単な問題を出したいと思います。
(わからなかった問題はしっかりと復習しよう!)
- 『和泉式部日記』のジャンルは何ですか。
- 和泉式部は誰と恋仲になりましたか、そのうち一人をあげなさい。
- 和泉式部の夫の赴任先は旧地名でどこですか。
- 和泉式部は藤原道長の娘に使えました、それは誰ですか。
- 『和泉式部日記』の特徴を「和歌」を使って説明しなさい。
→次回は源氏物語について解説します!
(註)
- [i] 現在の福井県北部にあたり。
- [ii] 第六三代天皇。名は憲平(のりひら)。村上天皇第二皇子。母は皇后安子(藤原師輔の女)。天暦四年(九五〇)生後二か月で立太子。康保四年(九六七)父帝の崩御によって即位し、在位二年にして弟の円融天皇に譲位した。在位中に安和の変が起きている。御陵は京都市左京区の桜本陵(さくらもとのみささぎ)。天暦四~寛弘八年(九五〇‐一〇一一)『日本国語大辞典』
- [iii] 没年:長保1.12.1(1000.1.10)、生年:天暦4(950)、平安中期の皇女,皇后。朱雀天皇と保明親王の娘煕子の皇女。母は出産後ほどなく没したので,父が寵愛,養育した「えもいはず美しき女御子」だった。その父も昌子が3歳のときに没すが,「后に立てたい」との遺言で,応和3(963)年2月28日14歳で東宮憲平親王(冷泉天皇)元服の日に副臥として入内,東宮妃。康保4(967)年冷泉即位の年,18歳で皇后となるが,冷泉天皇には狂気の行動が多く,しかも勢力ある摂関家の女性たちが入内したため,後見人の乏しい昌子は里第にこもりがちだった。子はなく,深く仏法に帰依し,石蔵(岩倉)観音院に荘園を施入したり供養を行ったりした。天延1(973)年皇太后,寛和2(986)年太皇太后。長保1年病が重く,和泉式部の夫橘道貞の三条邸で死去した。信仰に忠実に,西方に向かっての往生であった。庶民と同様,質素な葬送,土葬とすることなどを遺言し,石蔵観音院に葬られた。『新古今集』などに和歌が残る。『朝日日本歴史人物事典』
- [iv] 律令制で、内侍司の職員である尚侍ないしのかみ・典侍ないしのすけ・掌侍ないしのじようの総称。本来は天皇の日常生活に供奉ぐぶする女官であるが、平安中期には、妃・夫人・嬪ひんら天皇の「妾」に代わる存在となり、また、単に内侍といえば、掌侍をさし、その筆頭者を勾当こうとうの内侍と呼ぶようになる。『三省堂 大辞林 第三版』
- [v] 宮中に仕え、房(=部屋)を与えられて住む女官の総称。出身階級によって上﨟・中﨟・下﨟に大別される。また、院や諸宮・貴人の家などに仕える女性をもいう。『三省堂 大辞林 第三版』
- [vi] 没年:長和5.4.16(1016.5.24)、生年:生年不詳、平安中期の官人。広相の孫で下総守仲任の子。長徳1(995)年ごろ和泉式部と結ばれた。彼女の女房名は道貞が和泉守であったことによる。ふたりの間に小式部内侍が生まれている。結婚生活は幸福ではなかったようで寛弘1(1004)年陸奥守となったときには,ふたりは離れており,任国への下向の途次,尾張守大江匡衡,赤染衛門夫妻のところへ立ち寄っている。後年左京命婦と結ばれたらしい。権力者藤原道長に追従して,私邸を提供したり,馬を贈るなど典型的な受領であった。『朝日日本歴史人物事典』
- [vii] 現在の大阪府南部あたり。
- [viii] 977-1002 平安時代中期,冷泉(れいぜい)天皇の第3皇子。貞元(じょうげん)2年生まれ。母は藤原超子。弾正尹(だんじょうのいん)となり,のち大宰帥(だざいのそち)をかねる。長保4年病気により出家し,6月13日死去。26歳。和泉式部(いずみしきぶ)と恋愛関係にあったとつたえられる。 『日本人名大辞典』
- [ix] 981‐1007(天元4‐寛弘4)。平安中期の歌人。冷泉天皇の皇子。長じて大宰帥(だざいのそち)(遥任)となり,帥宮(そちのみや)とも呼ばれた。生母超子(ちようし)(藤原兼家の娘)の美貌をうけて容姿端麗であったうえに,文才に恵まれ,和歌のほか漢詩をもよくした。和泉式部との恋愛事件が衆人の関心を呼んだことは,《栄華(花)物語》や《大鏡》に詳しい。《和泉式部日記》中の和泉との贈答歌によって,その歌才のほどがうかがえる。 平凡社『世界大百科事典』
- [x] (966~1027) 平安中期の廷臣。摂政。兼家の子。道隆・道兼の弟。法名、行観・行覚。通称を御堂関白というが、内覧の宣旨を得たのみで正式ではない。娘三人(彰子・姸子・威子)を立后させて三代の天皇の外戚となり摂政として政権を独占、藤原氏の全盛時代を現出した。1019年出家、法成寺を建立。日記「御堂関白記」がある。『三省堂 大辞林 第三版』
- [xi] (988~1074) 一条天皇の中宮。道長の女むすめ。後一条・後朱雀両天皇を生み、道長による藤原氏全盛を可能にした。紫式部・和泉式部・赤染衛門らの才媛が仕えた。上東門院。『三省堂 大辞林 第三版』
- [xii] 大津市にある真言宗の寺院。762年頃、僧良弁が建立。初め東大寺(華厳宗)に属したが、平安中期に真言宗となり、朝廷貴族の崇敬を集めた。紫式部が本堂で源氏物語を書いたという。多宝塔は鎌倉初期の遺構で、和様の建築様式を伝える。西国三十三所第一三番札所。『三省堂 大辞林 第三版』
おすすめ記事
参考文献