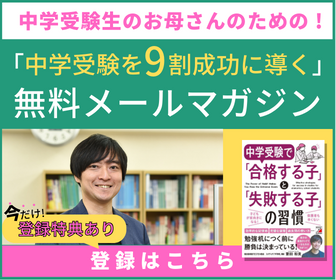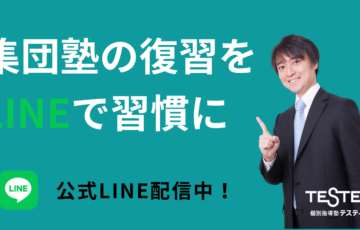『落窪物語』は4巻からなる平安時代中期の物語です。成立時期はおおよそ一条朝の初期、寛和~正暦(985~995年)など諸説あります。作者は未詳ですが漢文学の素養があり、和歌もよくする下級貴族の男性の手によるものだとする説が通説です。『落窪物語』は継子虐め譚を題材にしており、”日本版シンデレラ“と称されることもあります。『落窪物語』の“落窪”は主人公である女君が継母により「寝殿の放出の、また一間なる、おちくぼなる所の二間なる」(岩波文庫『落窪物語』より参照)ところに住まわされ、“おちくぼの君”と呼ばれていたことに由来しています。

まず、『落窪物語』のあらすじを紹介します。
昔、中納言忠頼には北の方との間に三男四女があったが、ほかに皇女腹に姫君が一人いた。北の方はこの継子の姫を、床の一段低いへや(落窪)に入れ、落窪の君と呼ばせて裁縫などに追い使った。姫の忠実な召使いの阿漕(あこぎ)に通っていた帯刀(たちはき)からこの事を聞いた左大将の子の左近の少将は見ぬ恋にあこがれ、やがて帯刀の手引きで逢うことができた。男の通うのを知った北の方は立腹して姫を塗籠(ぬりごめ)に押し入れ、六十余りの好色な典薬助に与えようとするが、阿漕の働きで難を切り抜ける。少将は、中納言一家の石山詣での留守に姫を救い出して自邸に隠し、継母への報復として、中納言の四の君の婿に、いつわって愚か者の兵部の少輔をさし向け、三の君の婿の蔵人の少将を自分の妹の婿に迎え、継母の清水参りや賀茂の祭見物に恥をかかせ、落窪の君の伝領した三条邸に中納言一家がひき移ろうとする矢先に乗り込んで嘆かせたりなどするが、やがて姫を父中納言と対面させ、そののちはうって変わってつぎつぎと恩恵を施し、姫と少将はいよいよ仲睦まじく栄華をきわめた。
(『国史大辞典』より参照)
以上の内容から『落窪物語』は、
- 第一部 継子虐め、少将による救出
- 第二部 継母らへの報復
- 第三部 少将、おちくぼの女君の栄華
の三部に分けることが出来ます。更に詳しく内容を見ていきたいと思います。
まずは主人公である“おちくぼの君”について。冒頭に「ときどき通ひ給ける、わかうど腹の君とて、母もなき御むすめおはす」(岩波文庫『落窪物語』より参照)とあるように、 “おちくぼの君”は正妻の娘ではなく、正式に結婚した相手でもない、いわば愛人格の娘です。母の死後、中納言邸で暮らしてはいますが、継母から裁縫などの労働を課せられ、召使同然の扱いをされます。また、当時貴族の娘は召使(女房)が数名いるのが普通ですが、おちくぼの君には”あこき”のみです。『落窪物語』の特徴として、おちくぼの君に仕える“あこき”と少将に使える“帯刀”という召使の二人の活躍があげられます。恋人同士である二人はおちくぼの君と少将を引き合せ結婚まで裏方で非常に大きな活躍をしました。
おちくぼの君は少将に見初められ結婚することになりますが、平安時代の正式な結婚は男が妻の屋敷に三日三晩訪れ、三日目に餅を食べるという儀式を行います[i]。しかし、おちくぼの君は親方の了解も得ずに結婚しているため、本来正妻の立場にはなり得ません。当時は一夫多妻制であるため、少将が他の身分の高い女性を正妻として迎えることも当時であれば当然の話ですが、少将はおちくぼの君を想うあまり他の妻を娶ることはせず、一夫一妻を貫きました。この点もこの物語の大きな特徴であるといえます。『落窪物語』は非常に当時の風俗を詳細に描いており、かなり女性の立場に寄り添った物語であると指摘されることもあります。
先ほど述べた「結婚の儀式」の場面を本文を参照しながら詳しく紹介していきたいと思います。 ※本文は全て岩波文庫『落窪物語』より参照。
- 1日目
父中納言と継母、その子らが石山詣[ii]に出かけ、連れて行ってもらえないおちくぼの君を不便に思ったあこきは「にはかにけがれ侍ぬ」と月の障り(生理)を理由に残ります。そこへ突然の少将と帯刀がやってきておちくぼの君と契りを交わすことになります。しかし、おちくぼの君は突然のことに戸惑い泣いてしまいます。その理由は自分自身が「ひとへ衣[iii]はなし。はかま一つ着て、所どころあらはに身につきたる」姿であることを恥じているのです。そのような不憫でいじらしい姿にはじめは愛人程度の関係で通おうと思っていた少将が心を変え、おちくぼの君を妻に迎える気になったのです。 - 2日目
おちくぼの君にはあこきしか女房がいないため、あこきは一人で奔走し、結婚の儀を執り行います。叔母に手紙を送り調度品を揃え、みすぼらしい服しかなかったおちくぼの君の身なりを整えます。間一髪のところで支度が整い、少将と帯刀がやってきて無事に2日目も終えました。 - 3日目
その日は天候が悪く大雨が降っており、少将と帯刀はおちくぼの君とあこきのもとに行くことを躊躇っていましたが、おちくぼの君のことを想い、悪天候の中出かけることにしました。傘を持って忍んで行った少将と帯刀ですが、途中下級役人に怪しまれ止められてしまいます。しかし、「まうとの少盗人は足白くこそ侍らめ」(訳:本当に盗人であったらこのように足が白いわけがない)とやり過ごすことが出来ました。
一難去ってまた一難、少将は「あはれ、これより帰りなん。糞つきにたり。いと臭くて、行きたらば中々疎まれなん」(訳:ああ、ここで帰ろう。糞がついてしまった。とても臭くて行ったら疎まれるだろう)と言います。暗い夜道を雨の中歩いているうちに少将は糞(馬や牛)の溜まり場に足を踏み入れ汚れてしまったのです。そんな少将に対し帯刀は「かかる雨にかくておはしましたらば、御心ざしをおぼさん人は、麝香[iv]の香にもかぎなしたてまつり給てん」(訳:このような雨の中いらっしゃったら、その御心ざしをきいた人は、麝香鹿[v]の香をたいてお迎えしますよ)と慰めます。その帯刀の言葉とおり少将がもう通ってこないと嘆いていたおちくぼの君は少将の深い愛を知り更に中を深めました。

以上のように、様々な困難がありながらもあこきや帯刀の活躍の甲斐もあって少将とおちくぼの君は結ばれます。平安時代の王朝文学は『源氏物語』をはじめ優美な印象が強いかもしれませんが、『落窪物語』では先に述べたように糞が出てくる場面もあり、どちらかというと下品なことまで詳細に描いています。このような点も『落窪物語』の特徴でしょう。更に、この物語の特徴として勧善懲悪が挙げられます。『シンデレラ』でもグリム童話の原作では、直接シンデレラが手を下した訳ではありませんが、継母、その娘たちに制裁が下されています。『落窪物語』でも、おちくぼの君が直接手を下す、または直接制裁を命じるような発言はしていませんが、主に少将によって継母らに制裁が下されます。その場面が描かれているのが『落窪物語』の第二部「継母らへの報復」になります。
この場面も詳しく見ていきましょう。
継母の娘である四の君の婿相手として少将が選ばれ少将のもとに縁談話がきますが、少将は既におちくぼの君の結婚している身であり、おちくぼの君以外の妻は娶らないと誓っています。そんな少将は縁談話をわざと受け、少将の代わりに面白の駒という顔が面白い(不細工)な男を逢わせ四の君と結婚させてしまいます。更に、清水詣[vi]や賀茂祭[vii]の見物の妨害をします。当時の貴族は牛車[viii]に乗りその中から祭の見物をしていました。見物する場所は位の高い貴族が優先的に場所を取れることもあり、しばしば祭では場所を争って貴族の従者たちが争う事件が起きていました。そのような争いの場面は『源氏物語』にも描かれています。

最後に描かれる報復は、「中納言一家が引っ越そうとしていた三条邸を奪い、おちくぼの君と少将の邸宅とする場面」です。しかしその後、中納言一家を邸宅に招き、おちくぼの君が少将の妻であることを知らせ、お互い和解したのです。しかし、継母だけは最後まで謝罪もせず態度は改善しませんでした。
最後に『落窪物語』に関する簡単な問題を出したいと思います。
(わからなかった問題はしっかりと復習しよう!)
- 『落窪物語』の“落窪”の由来は何ですか。
- 主人公は誰によって虐められていましたか。
- 主人公の召使(女房)は誰ですか。
- 主人公が結婚したのは誰ですか。
- 結婚し、成功した主人公は虐めた相手に対し報復を行いましたか。
→次回は枕草子について解説します!
(註)
- [i] 婚嫁(こんか)の際に行われた儀式の一つ。平安時代、貴族社会において主流を占めたいわゆる婿取り婚の婚儀では、結婚の開始から、毎夜男は女のもとへ通うのであるが、普通三日目の夜に餅(もち)を婿に供することが行われた。本来これは露顕(ところあらわし)の儀と一体のもので、その本質は、自家の女性の寝所に忍んで通う男を、その現場でとらえ、自家の火で調理した餅を食べさせることで同族化してしまうという婿捕(むことら)えの呪術(じゅじゅつ)の儀式化といえる。露顕の際には、婿は舅姑(しゅうとしゅうとめ)以下と対面、披露の宴が催され、新婦側は婿の従人を饗応(きょうおう)した。餅の種類、数などには諸説あるが、『江家(ごうけ)次第』は、銀盤に餅三枚をのせて供し、婿はそれを全部は食い切らないのを作法としている。小学館『日本大百科全書』
- [ii] 〘名〙 滋賀県大津市の石山寺にまいること。特に陰暦一〇月甲子の日に参詣すること。『日本国語大辞典』
- [iii] 袿(うちき)の下に着る裏のない下着。岩波文庫『落窪物語』注釈より
- [iv] 麝香鹿の雄の分泌器官から作る香料。「じゃかう」とも。岩波文庫『落窪物語』注釈より
- [v] 偶蹄目ジャコウジカ科の哺乳類。体長90センチメートル、肩高60センチメートルほど。雄の上顎犬歯は長く牙状で、角はない。へその後方に麝香を分泌する麝香腺がある。中国南部から東アジアの山地の森林に三種が生息する。三省堂『大辞林 第三版』
- [vi] この現世利益の観音信仰が,平安中期から高まると,当寺は学問や修行の寺としてよりは,信仰で栄える寺となり,日本無双の観音霊場とうたわれた。平安時代以来,種々の〈清水寺縁起〉がつくられて,霊験譚が世に喧伝され,貴賤の参詣者や参籠者が境内にあふれ,〈清水詣(もうで)〉なる言葉も生まれた。清少納言は毎月18日の観音の縁日に参籠する人で当寺がにぎわうのを〈さわがしきもの〉と伝え,《源氏物語》夕顔の巻には〈寺々の初夜も,皆,行ひはてゝ,いとしめやかなり,清水の方ぞ,光多く見え,人のけはひもしげかりける〉とあるなど,平安文学の素材に当寺の信仰が登場する。『世界大百科事典』
- [vii] 京都の、賀茂別雷神社(かもわけいかずちじんじゃ)(=上賀茂神社)と賀茂御祖神社(かもみおやじんじゃ)(=下鴨神社)の祭例。古くは四月第二の酉(とり)の日、現在は、五月一五日に行なわれる。祭の前の午(うま)または未(ひつじ)の日に、賀茂川で斎院の御禊(ごけい)がある。京都鎮守の祭で、平安時代には特に盛大となり、単に祭といえばこの祭を意味した。葵の葉で牛車や簾(すだれ)、社殿や祭人の冠(葵鬘(あおいかづら))などを飾り、賀茂の家々の門にも葵をかけたので、葵祭ともいう。石清水八幡宮の南祭に対して北祭といわれることもある。『日本国語大辞典』
- [viii] 主に平安時代、牛にひかせた貴人用の車。屋形の部分に豪華な装飾を凝らしたものが多く、唐庇からびさしの車・糸毛の車・檳榔毛びろうげの車・網代あじろの車・八葉の車・御所車などがあり、位階や公用・私用の別によって乗る車の種類が定められていた。うしぐるま。ぎゅうしゃ。三省堂『大辞林 第三版』
おすすめ記事
参考文献
- 岩波文庫『落窪物語』
- 『国史大辞典』
- 『新国語要覧』大修館書店
- 『改訂新版・世界大百科事典』平凡社
- 『三省堂 大辞林 第三版』
- 『精選版 日本国語大辞典』小学館
- 山川出版社『日本史研究』
- 小学館『日本国語大辞典』